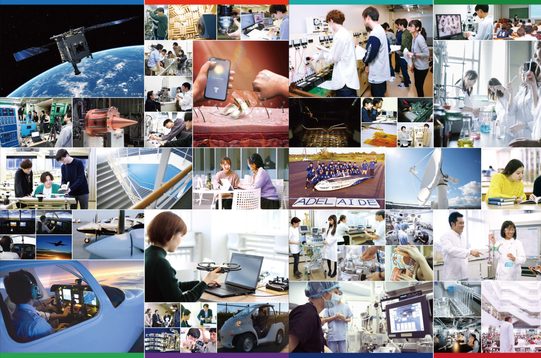大学院工学研究科機械工学専攻の高橋翔大さん(1年次生、指導教員=木村啓志教授)が、3月13日に早稲田大学で開催された日本機械学会関東支部「第63回学生員卒業研究発表講演会」で学生優秀発表賞を受賞しました。同講演会の発表者の中から特に優れた口頭発表に送られるもので、今年度は240余りの発表の中から26人が選ばれ、本学からは高橋さんが受賞しました。

高橋さんの発表テーマは、「シグナル物質に対する細胞応答の観察に向けたマイクロ流体デバイスの開発」です。研究の背景には、少子化の一つの要因ともされる男性不妊症について、その主たる原因である精子形成障害の早期発見?治療の方法を確立するために待たれる精子形成のメカニズムの早急な解明があります。精子の元であり、自らも増殖する精子幹細胞は、生体内で濃度が変動するシグナル物質にさらされていることは知られていますが、その応答については不明です。そこで高橋さんは、細胞の応答を詳細に観察することのできるシステムの開発を目指して研究を進め、これまで木村教授の研究室で進められてきたマイクロ流体システムを応用し、送液などを安定させることでシグナル物質の長周期的な濃度変化を再現可能な「2層型流路デバイス」の実現を試みてその経緯を発表。高い評価を受けました。
高橋さんは、「2層型流路デバイスを使い、多孔膜で仕切られた上層で培養された細胞が、下層流路を流れる物質に曝露されることを確認しました。また、送液流量を変えることで濃度の時間制御が可能なこと、流路幅?方向に応じて濃度分布の形状に差ができることなどがわかり、シグナル物質の時空間的濃度勾配の形成が可能であることが示唆されました」と研究成果を振り返りました。受賞について、「スーパーサイエンスハイスクール(SSH)の出身で、高校時代からプレゼンテーションに挑んできたものの、実は苦手でした。それが大学の研究室で仲間と発表の練習をするなどして成長を実感できるようになり、今回の受賞につながったと思います。仲間に感謝したい」と喜びを語りました。今後の抱負について、「さらに微小空間制御の精度を高める研究に取り組み、社会に役立つデバイスの設計開発をしていきたい」と意気込みを話しています。
木村教授は、「高橋さんはまじめな努力家であることに加え、自ら考えアイデアを具現化する実行力があります。同期も皆、明るく前向きに研究に取り組んでおり、切磋琢磨しています。これからの成長を楽しみにしています」と話しています。